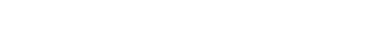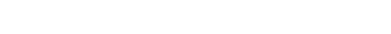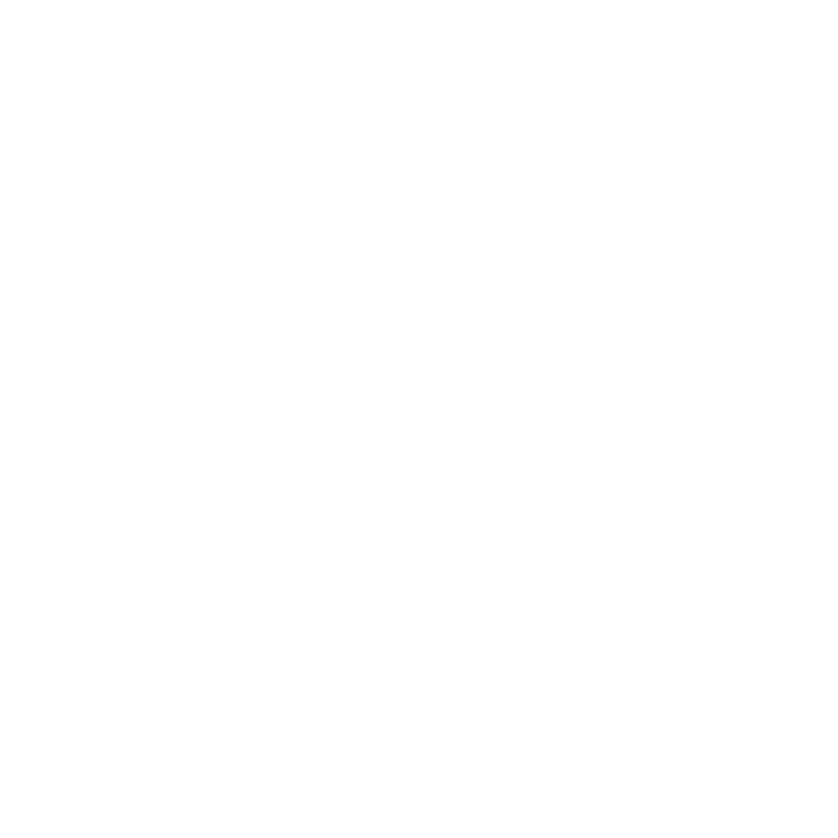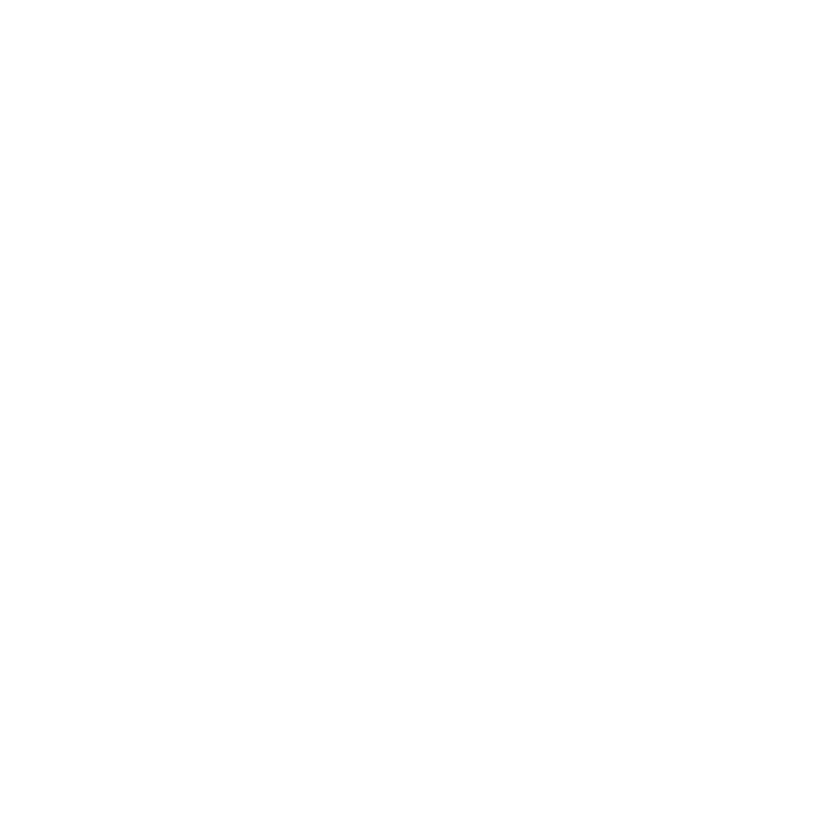- 日本史(古代/中世/近世)
- 日本美術史
- ジェンダー史
古文書や古記録、美術品の調査や聞き取り調査など、現地でのフィールドワークをも取り入れながら、多面的に歴史研究を進めています。
- 世界遺産学
- 日本考古学
- 保存修景論
- 民俗学

全員が1年間の環琵琶湖文化論実習(2泊3日のフィールドワークを含む)に参加し、滋賀県の歴史・文化に関するテーマを各自研究します。各分野の基礎科目を学びます。
3年次のゼミ配属に向けて、各教員の「プレゼミ」に参加し、自らの興味・関心のありかを探っていきます。各分野の基礎・専門科目を学びます。
原則として2年間、同一ゼミに所属し、専門的学習を深め、自分で見つけたテーマについて調査・研究を行い、卒業論文をまとめます。
- 日本文化論
- 日本史概説
- 日本史料講読
- 芸術学
- 考古学
- 東アジア考古学概論
- 地域文化財論
- 民俗学
- 東洋史概説
- 現代中国論
- 日本社会論
- 人文地理学
- など
1年次に履修できる学科基礎科目:
- 歴史的地域論
- 近世近江論
- 地域経済史論
- 古文書演習
- 美術史
- 比較文明論
- 考古学特論
- 考古学実習
- 文化財・保存修景論
- 民俗学特論
- 中国地域文化論
- 朝鮮地域文化論
- 東アジア世界論
- 文化社会学
- 人文地理学
- 地誌学
- 地域と経済
- 地域と行政
- など
2〜4年次に履修できる学科専門科目:
- 「うたたね草紙絵巻」研究
- 「星光寺縁起絵巻」の研究
- 藤田嗣治筆「アッツ島玉砕」研究
- 歌川国芳筆「里すゞめねぐらの仮宿」研究
- 川瀬巴水研究
- 生理にまつわる困難とその対策
- ミュージカル映画におけるLGBT表象―“多様性”から“インクルーシブ”へ―
- 江戸時代の男色文学にみえる名所
- 錦絵新聞からみる人々の関心―錦絵版「東京日々新聞」と錦絵版「郵便報知新聞」を通して―
- 第2回内国勧業博覧会における外国人への対応
- 近世近江の材木流通―安曇川流下材木と船木材木座を事例に―
- 寺子屋史料から読み取る時習斎の教育―近江商人の特性と繫がる寺子屋師匠の教え―
- 『蔗軒日録』に見る漢籍受容
- 戦国期近江浅井氏の文書発給
- 戦国期近江六角氏の家臣団構造-伊庭氏を素材として-
- 中世後期の近江国葛川における山林資源管理
- 近江における「椿井文書」の形成について-伊香立の竜骨からみる椿井家由緒の成立
- 歴史 -
- 鳥のむそう網猟をめぐる環境民俗学的考察
- 念仏踊りの継承に関わる人々-長崎県五島市富江町のオネオンデを中心に-
- 月経をめぐる民俗
- 流しびなを支える人々
- 大阪府・京都府・滋賀県における備前焼の流通
- 中世都市出土の遺存体からみる動物利用の復元-堺環濠都市遺跡を中心に-
- 近江における山茶碗の様相
- 水口曳山祭における山蔵の保存・維持に関する研究-柳町を事例として-
- 湖東地域における浄土真宗寺院の太鼓楼に関する研究
- 中山道赤坂宿における町なみ景観の基礎的研究
- コミュニティ施設に活用した伝統的建造物の活用方法に関する研究-岐阜県内の施設を事例として-
- 近世における瓦師および瓦屋の動向に関する研究-近江八幡市を中心として-
- 歴史的町並みの保存活動に関する研究-滋賀県彦根市河原町芹町地区を事例として-
- 彦根藩足軽屋敷・旧北川家住宅の復原的研究
- 弥生・古墳時代における木製農耕具生産-近江地域出土の直柄平鍬を中心に-
- 古墳時代における金銅製冠副葬の意味
- 日本列島出土の八鳳鏡の性格
- 深鉢の容量からみる縄文時代琵琶湖周辺地域の食生活
- 地域遺産 -
- ゲイ男性の恋愛観-同性婚との関係性-
- 滋賀県のベトナム人住民-同胞との関わりに着目して-
- ガールズバーの民族誌
- だめライフ愛好会に集う若者が追求する「だめであること」について
- 交流 -
- 連節バスの導入事例と今後のバス交通
- 北陸新幹線の福井・敦賀延伸に伴う福井県の観光まちづくりに関する考察
- ブルワリーの観光資源としての役割-滋賀県長浜市を事例として-
- 大学におけるGIS教育の現状と課題
- 現代社会における寺院と檀家の関係
- 身近な水域とその対岸に向けられる琵琶湖の親水意識の考察
- 高齢化地域における住宅の緑地空間の維持管理に関する研究-滋賀県草津市若草地区を事例として-
- 景観資産登録制度が適用された農村地域の景観まちづくりに関する研究-京都府亀岡市川東地区を事例として-
- パークマネジメントにおける指定管理者制度の適用実態-岐阜県岐阜市の境川緑道公園を事例として-
- 宿場町における景観構成要素に関する課題の特徴-旧東海道土山宿景観保全に関わるまちづくりを事例に-
- スポーツマンガにおける「才能」の描写の変遷-『SLAM DUNK』から『THE FIRST DUNK』へ-
- 滋賀県の交通安全の現状と課題-高齢者に注目して-
- 多様化する音楽フェスにおける環境への取り組みに関する考察
- プロスポーツチームを活用した地域活性化-新球団誕生の静岡市を事例として-
- 滋賀県の平和教育について-滋賀県平和祈念館の歴史と活動にみるダークツーリズム批判-
- 若者文化としての鞄の装飾について-Z世代におけるキャラクターグッズの受容とその利用-
- 恋愛・性愛の多様性-アロマンティック/アセクシュアル・スペクトラム当事者への聞き取り調査を通して-