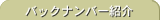
2000年1月の創刊号より現在に至るまでの人と地域のバックナンバーを紹介します。
>> 第26号〜第30号
>> 第21号〜第25号
>> 第16号〜第20号
>> 第11号〜第15号
>> 第06号〜第10号
>> 第01号〜第05号
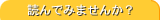
人と地域は、興味・関心のある方に無料でお届けいたします。ご希望の方はこちらまで。また、滋賀県内の中学・高校、図書館でも読むことができます。
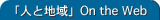
 各号紹介の左記のマークがあるものについては、オリジナルの出版と同じものをPDF形式で表示・印刷することができます。表示・印刷にはアドビシステムズのAcrobat Readerが必要になります。ほとんどの場合お使いのコンピューターにプリインストールされていますが、ない場合は最新のAcrobat Readerをインストールしてください。 各号紹介の左記のマークがあるものについては、オリジナルの出版と同じものをPDF形式で表示・印刷することができます。表示・印刷にはアドビシステムズのAcrobat Readerが必要になります。ほとんどの場合お使いのコンピューターにプリインストールされていますが、ない場合は最新のAcrobat Readerをインストールしてください。

こちらからダウンロードできます。
|
|
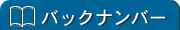 |
 |
第20号 心の泉 |
 命の輝き見えますか。 命の輝き見えますか。
「私」と親友、おじいちゃんとの思い出を通して、自分と家族とは、地域とは、と思いをはせた作品。おじいちゃんとおばあちゃんの結婚にいたる話、子供の頃怒られた思い出、そして…おじいちゃんの死。「私」は泣いて泣いて、とまらない涙とともに詩を書きました。「私」は言います。「つらくて かなしくて どうしようもなくて おもいっきり心が揺れるから 胸に響いて涙がこぼれてしまいます。」
ひとりの「心の泉」がどのように揺れ動いてきたのか、みなさんみてください。
|

田中美登里
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成13年度卒業生。
「心の泉」は卒業論文。
|

『人と地域』がリニューアルしてから初めて発行された「心の泉」。著者とは4年間をともにすごしてきた友人です。著者に対する思い入れもさることながら、作品そのもののすばらしさに編集させてもらえる有難さをかみしめながらの作業でした。(武藤恭子)
|
 |
第19号 あんなインド、こんな二人 |
 |
 麻子と陽子の珍道中日記。 麻子と陽子の珍道中日記。
二人は今度の旅行で本当の親友になったようだ。これは大きな収穫だ。本文を読んでいただければわかるのだが、麻子が下痢で死にかけた。もう一日遅れてたら脱水で死んでいたに違いない。もう死ぬのではないかと思った麻子と、介護する陽子は本当に極限状態にあったようだ。そんな中で二人は一瞬だがむき出しの自分を相手に見せている。極限状態で現す醜さ、弱さ。だが、そんなものを出しあったうえで、二人は一皮むけている。そしてこの相手となら今後もやっていける、という実感をえる。彼女たちは本当にいい旅をしていたと思う。(高谷好一「学生と旅」より)
|

福岡麻子と村田陽子
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成14年度卒業生。
インドでの珍道中を日記をもとにまとめあげた。帰国後も各分野に引っ張りだこの人気者で、地元彦根の中学校での出前講演会まで引き受けてしまったほど。
|
 |
第18号 女の道 |
 |
 只今、作成中... 只今、作成中...
|

後藤魅妃
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成13年度卒業生。
「女の道」は卒業論文。
|
 |
第17号 心でみたもの、感じたキモチ |
 |
 私のアカンタレ紀行 私のアカンタレ紀行
ペルーやチリでこれでもかというほどアカンタレぶりを発揮した私は、このアカンタレな人間が私なのであればそれはそれでいいのではないか?とある種の開き直りではありますがそう思ったのです。(あとがきより)
南アメリカの旅で自分自身を見つめ直した著者の青春のアカンタレ紀行。
|

中田春奈
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成14年度卒業生。
「心でみたもの、感じたキモチ」は3回生のときに行った南米旅行を綴ったもの。
|
 |
第16号 「僕の見た中国」 |
 |
 行ってみてはじめてわかるホントの中国。 行ってみてはじめてわかるホントの中国。
成都に向かうバスの中。助手席にバケツいっぱいの水がある。バスが揺れるたびにその水が僕の靴を濡らしていた。僕はその水の使い道を考えていたが、どうやらエンジンを冷やす為にあるようだ。日本では考えられないことなので、自分の乗るバスが無事に走るのかどうかを心配していた。(本文より)
|

青山 繁
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成13年度卒業生。
「僕の見た中国」は3回生のときの中国旅行の記録。
現在は彦根市内の喫茶店でコーヒーの修業中。 |
|
|