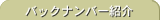
2000年1月の創刊号より現在に至るまでの人と地域のバックナンバーを紹介します。
>> 第26号〜第30号
>> 第21号〜第25号
>> 第16号〜第20号
>> 第11号〜第15号
>> 第06号〜第10号
>> 第01号〜第05号
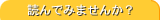
人と地域は、興味・関心のある方に無料でお届けいたします。ご希望の方はこちらまで。また、滋賀県内の中学・高校、図書館でも読むことができます。
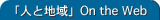
 各号紹介の左記のマークがあるものについては、オリジナルの出版と同じものをPDF形式で表示・印刷することができます。表示・印刷にはアドビシステムズのAcrobat Readerが必要になります。ほとんどの場合お使いのコンピューターにプリインストールされていますが、ない場合は最新のAcrobat Readerをインストールしてください。 各号紹介の左記のマークがあるものについては、オリジナルの出版と同じものをPDF形式で表示・印刷することができます。表示・印刷にはアドビシステムズのAcrobat Readerが必要になります。ほとんどの場合お使いのコンピューターにプリインストールされていますが、ない場合は最新のAcrobat Readerをインストールしてください。

こちらからダウンロードできます。
|
|
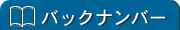 |
 |
第15号 考えるあたま、感じるこころ -地域学序説- |
 けっきょく「地域」ってなんだろう。 けっきょく「地域」ってなんだろう。
岸川 綾はユニークな人である。地域が大事だといい続けている私たちのゼミで、「自分には地域というのはどうもわからない」といい続けてきた。ある意味では異端である。だが、ゼミの中では最も献身的な働き手である。研究会の下準備を引き受けたり、『人と地域』でも製本や発送など縁の下の力持ちの役目を積極的にやってくれている。(高谷好一「心あたたかい「まち」の人」より)
|

岸川 綾
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成13年度卒業生。
「考えるあたま、感じるこころ」は卒業論文。論理だけでは成り立たないこころの学問についての深い考察。
|
 |
第14号 伊吹のこころにふれて |
 |
ふるさと伊吹のこころ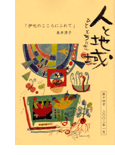
私の祖父と祖母にも、聞き書きをよんでもらいました。
「これは立派な文化や。永遠に残していってな。」と言ってくれました。私も、本当にそう思います。これからの伊吹町を担う私たちの世代が、昔からの伝統や文化をしっかりと受け継いでいかなければいけません。この聞き書きは、自信を持って次の世代、また次の世代へと伝えていきたいと思います。(奥井淳子「おわりに」より)
|

奥井淳子
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成13年度卒業生。
滋賀県伊吹町に生まれ育つ。
「伊吹のこころにふれて」は卒業論文。
|
 |
第13号 南の島 西表島からの語りかけ |
 |
 自然・地域に生きる。 自然・地域に生きる。
旅に明け暮れた学生生活。その最後の旅に、著者が選んだのは沖縄、西表島だった。
通過者としてではなく、生活者としての視点で見つめた西表島。住み込み生活を通して、そこに生きる人の姿を描く。
生活、農業、自然保護・・・。外からの目では決して見ることのできない西表島の現実と向き合い、彼は自らの人生に問いかける。
|

勝山雅和
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成12年度卒業生。
「南の島 西表島からの語りかけ」は卒業論文。
卒業後、旅行代理店勤務を経て、現在はなぜか警察官。
|
 |
第12号 「やま」と「ひと」 |
 |
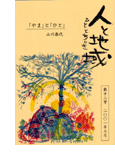 羽黒修験を体験して 羽黒修験を体験して
幼い頃から山が好きだった。祖母から山奥での暮らしを聞き、山で毎日遊んだ。大学生になった作者は、「山での生活ができる場所」を求めて参加した修験道で、自然によって生かされている自分を体感する。幼い頃から山が好きだった。祖母から山奥での暮らしを聞き、山で毎日遊んだ。大学生になった作者は、「山での生活ができる場所」を求めて参加した修験道で、自然によって生かされている自分を体感する。
|

山川恭代
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成12年度卒業生。
「やま」と「ひと」は卒業論文。
|
 |
第11号 人と生きる |
 |
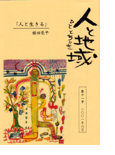 それでも、ひとは生きている。 それでも、ひとは生きている。
僕は旅でさまざまの人と出会った。同じ日本人、同年代の学生、世代の違う人たち、外国人、現地で暮らす人々、僕はその出会いの中で多くのことを感じた。そして僕自身もかわったように思う。
最初はそれを「旅行記」としてひとつの形のしようと考えた。しかし自分自身の変化を考えたとき、それを「旅」という言葉だけではどうしても言い表すことができなかった。そこには生い立ちがあり、親があり、それまでの出会いがある。すべてが僕のなかで関わりあって今の僕がいる。今考えていることを、今書くことに大きな意味があると思う。
「僕が今生きていること」をこれまでのすべてに感謝して振り返ってみたいのである。(本文より)
|

植田亮平
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成11年度卒業生。学生時代に数々の海外旅行を体験。「人と生きる」は卒業論文。
|
|
|