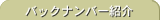
2000年1月の創刊号より現在に至るまでの人と地域のバックナンバーを紹介します。
>> 第26号〜第30号
>> 第21号〜第25号
>> 第16号〜第20号
>> 第11号〜第15号
>> 第06号〜第10号
>> 第01号〜第05号
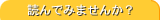
人と地域は、興味・関心のある方に無料でお届けいたします。ご希望の方はこちらまで。また、滋賀県内の中学・高校、図書館でも読むことができます。
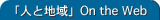
 各号紹介の左記のマークがあるものについては、オリジナルの出版と同じものをPDF形式で表示・印刷することができます。表示・印刷にはアドビシステムズのAcrobat Readerが必要になります。ほとんどの場合お使いのコンピューターにプリインストールされていますが、ない場合は最新のAcrobat Readerをインストールしてください。 各号紹介の左記のマークがあるものについては、オリジナルの出版と同じものをPDF形式で表示・印刷することができます。表示・印刷にはアドビシステムズのAcrobat Readerが必要になります。ほとんどの場合お使いのコンピューターにプリインストールされていますが、ない場合は最新のAcrobat Readerをインストールしてください。

こちらからダウンロードできます。
|
|
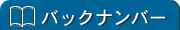 |
 |
第10号 旅 -アジア連帯の可能性- |
 旅から考えるアジア 旅から考えるアジア
ある人がどこかへ行って、人と出会って、感じて、旅についてあれこれ考えた・・・。
2001年1月に脱稿した私の卒業論文は、2つの旅を基軸に、心に漫然と渦巻いていた不安へと視線が注がれています。
その不安は「人」の存在さえ、どんどん薄れていく忙しい日々の中で、何を拠り所に「正しさ」を求めればいいのか、どこに足を踏ん張って未来を見ればよいのか、これらに答えをが出せな脆さから、今も次々と生まれています。
旅は日常から離れて移動すること、と定義されていますが、日常から目を背けることはありません。むしろ日常から離れることで、自分の居場所が明らかになるのです。
体験、つまりは頭でなく体で知ることが旅の醍醐味といわれています。しかしここでは、その衝動、震動、感動をもたらした「旅」そのものは一体何なんだろうかと、思考という静かな海を探ってみることにしました。
みなさんに心にも、それぞれの形をしたさざなみが立つでしょう。
すべての方々は、旅とは無縁ではないはずだからです。(本文より抜粋)
|

小川加容子
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成11年度卒業生。
「旅 ーアジア連帯の可能性ー」は卒業論文。
|
 |
第9号 近江の地にいきづく近代建築 |
 |
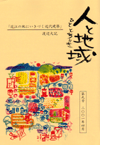 近代建築から見る人と地域の姿 近代建築から見る人と地域の姿
地域に残っている建物は前々から私に、何かしらの独特の雰囲気を感じさせていた。それは現代の建築にはない、風格・あたたかみとでもいうべき人間臭さというものなのではないだろうか。私は最初、今回は建物に絞って調べようと思っていたが、それだけではこの建物の良さは分からないのではないかと思うようになった。そこにはバーチャルな世界にはない、ぬくもりのある人と人とのつながりがあるからである。(本文より)
|

渡辺大記
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成14年度卒業生。
「近江の地にいきづく近代建築」は2回生のときに書いたもの。
執筆精神旺盛な彼は、「人と地域」最多の執筆回数を誇る。
|
 |
第8号 青空 曇り空 |
 |
 小西洋子のインド・ネパール紀行。 小西洋子のインド・ネパール紀行。
インド病とは、ある本によると次のように記されている。
インド病・・・インドでかかる心の病気。特徴は、
1.何かものを言うとき最初に「インドでは・・・」と言う。
2.買物をするときやたらと値切る。
3.仕事がいやになって怠け者になる。
4.とにかくインドが恋しくなる。
一度かかってしまうと、インドへ行くしか治療法はないらしい。(本文より)
インド病にかかってしまった著者のインド・ネパール紀行。インドで彼女を待ちうけていたものは・・・。
|

小西洋子
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成14年度卒業生。
はじめてインドに行って以来アジアの虜になってしまった。「青空 曇り空」は1回生の終わりごろにインド、ネパールを旅したときのもの。
|
 |
第7号 雫 |
 |
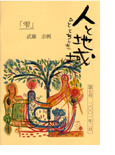 ここに一滴の雫を置きます。 ここに一滴の雫を置きます。
私は確かにここにいるのに、でもどこにいるのかわからない。私は確かに日々を過ごしているのに、でも、何をしているのかわからない。体が地につかないような、自分だけがかりそめの世界にいるような、そんな寂しさを感じたことはありませんか?これは、私がそんなかりそめの世界から、心のよりどころとするもの、自分の核のようなものを見つけるまでの心の旅路です。どうぞ、ひととき、あなたの旅の足を止めて、私の旅路を垣間見てください。(本文より)
|

武藤志帆
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科平成12年度卒業生。
「雫」は卒業論文。詩の形式で卒論を提出したのはおそらく県大史上初の試み。 |
 |
第6号 顔は同じ、中身は中華風味 |
 |
 大坪寛子の中国珍道中 大坪寛子の中国珍道中
大学に入り、毎日講義で難しいお話を聞いていると、つくづく自分の無学さに嫌になり、先生方が何を言っておられるのかわからないことが多々出てきます。けれども、幸いなことに私達のまわりの先生や先輩は、とっておきの「もうひとつの勉強」の方法を教えてくれます。それは、自分の眼で実際に見てみること、触れて空気を吸ってみること。やってみること。こんなに楽しくて分かりやすい勉強がどこにあるでしょうか。これなら私にもできそうな、がんばれそうな気がします。
春休みの始まる前、思いつきで中国に行くことを決め、約1ヶ月ほどひとりで大急ぎで歩いていきました。旅行中、中国があまり好きになれなかったのですが、帰ってきてからなぜかあの中国人のあの「他人のことはお構いなし精神」が気になって、顔は似てるけど中身は全く違う、そんな人々にとっても夢中になりました。あのどでかい国はたくさんの民族と探せば探すほどいろんな景色があって決して1度で走ることはできないと思いす。だから、「未知の中国」が、まだまだありそうです。気がつけば今、とっても私は中国が好きです。私の眼に映った中国と、おもしろおかしな光景を少しでも分かっていただければ幸いです。そのためにも、ここには限りなく等身大の自分を入れておきました。(本文より抜粋)
|

大坪寛子
滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科5期生。
彼女もまたアジアに魅了されたひとり。「顔は同じ、中身は中華味」は1回生の終わりの旅でのお話。中国に魅了された彼女は留学をすることになる。
|
|
|