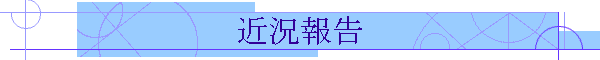
|
|
|
|
|
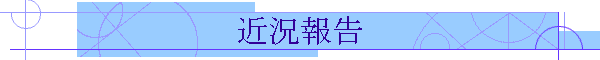
『人間文化』には一応毎年報告を掲載しているのですが、Webの更新を怠っています。申し訳ございません。
人間文化学部発行の『人間文化』に掲載されている「近況報告」記事です。
2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002
本学に赴任して5年目、多くの方々のご協力を得ながら滋賀県下での在日朝鮮人高齢者からの聞き取り調査にようやく着手しました。なかなか思い通り進まず難儀していますが、無年金問題など在日高齢者を取り巻く実情、地域の語られなかった歴史に触れ、不勉強を恥じつつ、私の立場やなすべきことを絶えず問い直される思いです。
このところの「嫌韓流」ブームへの批判本の企画へ参画する機会があり、1節担当しました。他に執筆中のものは、私が締め切りを守れなかったためにまだ発表されておりません。このような仕事が「多重債務」化する事態がますます深刻になった一年でした。
教育面では、前年度に引き続きレスポンスカードを毎回提出してもらい、授業づくりに役立てたつもりです。成績処理終了後、レスポンスカードやレポートを赤ペンでコメントを書いて談話室を通じて返却しているのですが、受け取りに来ない学生もいて残念です。前期開講科目のレポート仮題で、インターネットからの安易なコピー&ペーストが今までになく目についたので、後期開講科目ではレポートの書き方等について、通算で1コマ分以上かけて説明しました。公開講座受講生で一通り私の提供科目を聴き終えた方が、来年はもう無いのですかと残念そうにおっしゃってくださったことが、今年度最大のご褒美でした。
地域との関わりでは、冒頭に述べた在日朝鮮人への聞き取り調査に一番労力を注ぎました。そのこととも関連して、予期せず旧能登川町史の執筆委員となりました。在日朝鮮人の歴史を自治体史に書き込むという未知の仕事を前に、やる気だけは満々です。
最後に、朴慶植文庫についてですが、昨年度末に何とかまとめて発行させていただいた仮目録を各方面に発送し、励ましと感謝の言葉をたくさん頂戴いたしました。今まで頼っていた院生が卒業してしまい、今年度は少々整理が滞りましたが、閲覧や取材などの問い合わせも多く、頑張らねばとの思いを新たにしています。
Ⅰ.研究活動
(1)受賞
(2)著書
田中宏・板垣竜太編『日韓新たな始まりのための20章』岩波書店、2007年(共著)
(3)研究論文
(4)報告書(科研,受託研究費,等)
『朴慶植文庫仮目録2』滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科、2006年
(5)学会口頭発表
「私たちは何を忘れさせられているのか」女性史総合研究会5月例会(2006年5月20日)
「「一国史」「男性史」も、「足し算」も越えて ― 朝鮮史/女性史の立場から」合評会・東アジア歴史共同教材をめぐって(2006年12月10日)
(6)競争的資金(研究組織,タイトル,研究費を明記)
学内特別研究費
滋賀県立大学特別研究費(奨励研究)「滋賀県における在日朝鮮人に関する歴史教材・資料集の編纂に向けた調査」
民間研究助成
日本証券財団研究調査助成「滋賀県における在日コリアン1世の生活史に関する聞き取り調査」(研究協力者)
Ⅱ.地域・社会・国際貢献
(1)講演会・展覧会
膳所高等学校教職員人権研修会講師(2006年6月23日)
彦根市保育協議会人権研修・コーディネーター・司会(2006年7月1日)
「差別をなくし人権を尊ぶ彦根市女性のつどい実行委員会」研修講師(2006年8月22日)
「人権学習をすすめる真野学区市民のつどい」講師(2007年2月24日)
河合塾文化教育研究所・日韓文化研究会講師(2007年3月1日)
(2)出張講義等
KEIBUN文化講座第18期・知っていますか?在日コリアン(2006年9~11月)
(3)各種審議会・委員会委員
東近江市史調査執筆委員(2006年9月1日~)
彦根市外国籍市民施策懇談会委員(2005年9月~)
「人権教育における授業と教材に関する研究集会」(滋賀県人権教育研究会主催、2006年11月10日)分科会研究協力者
(4)学会委員会委員
朝鮮史研究会関西部会幹事
朝鮮史研究会論文集編集委員会委員
女性史学編集委員会委員
(5)総説,一般向け(雑誌・新聞等)記事
「「不審者」情報にひそむ外国人差別」『多民族共生』Vol.63・64合併号(2006年8月29日)
「地球市民しが」『じんけん』No.303(2006年7月)~(隔月連載)
【教育活動】
今年から出席カードにかえて、少し大判の「レスポンスカード」をつくり、毎回出させるということをはじめてみました。もうすこし効果的な活用方法もあったのではと反省点もありますが、話したつもりなのに理解されていないことがわかるなど、授業づくりに役立ちました。
ゼミでは、彦根・米原に現存する、在日朝鮮人が「帰国事業」の際に残していった銅像を見学し、その由来などについて調べ、ホームページにも掲載しました。像の由来についての詳細は本誌掲載の稲継靖之さんの論稿をご参照下さい。稲継さんは修士論文で滋賀県の在日朝鮮人の歴史をまとめ上げ、大変喜んでいます。今年は4回生も堅田に絞った在日朝鮮人史で卒論を書きましたが、今後、稲継さんの研究を土台に、これからもゼミの後輩たちが県内の在日朝鮮人について個別に調査を進め、地域史の中に在日朝鮮人の存在をしっかりと位置づけて行ければと思います。
【研究活動】
5年前にNHKのドキュメンタリー番組が改ざんされた事件をきっかけに立ち上がった時から私も関わってきた、メディアの危機を訴える市民ネットワーク(メキキネット)編で『番組はなぜ改ざんされたか』(一葉社)が刊行されました(私が書いたのはごくわずかですが…)。2006年1月28日に京都で出版記念シンポを開催し、パネラーとして少し話しました。
今年は中学校の教科書採択があり、滋賀県では河瀬中学で扶桑社版教科書が採択されるというショッキングな出来事がありましたが、日本科学者会議滋賀支部で機会をいただき、「中学校歴史教科書にみる植民地関連記述の検討」を2月4日に報告しました。
朴慶植文庫整理は、特別研究費が付かなかったのですが、ノウハウのある学生が在学しているうちに少しでも進めようと一般研究費で細々と整理しました。日本国内の研究者のほか、韓国からは、日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会の訪問がありました。強制連行研究を切り開かれた朴慶植先生の資料が、韓国の真相糾明委員会の活動やそれに協力する日本の市民団体の活動に役立つよう、今後も協力していきたいと思っています。
自分の研究らしい研究はほとんど進まず、焦燥感もありますが、育児時間休暇を取得して(減給もされて)おり、研究不振はその育児時短分だと自分を納得させています(校務は環琵琶湖文化論実習以外は従前通りこなしているつもりなので…)。
【地域活動】
比較的大きなイベント二つについては、本誌掲載の報告記をご参照下さい。その他、以下のような場で講師その他をする機会が急に増えました。2005年度滋教組湖東1・2支部学習会・講演「一緒に考えてみませんか?共生社会をつくる学校教育とは?」講師(2005年6月4日)/KEIBUN文化講座「「朝鮮半島と日本・近江」(2005年9~11月)/第49回滋賀県人権教育研究大会の特別分科会(11月13日、研究協力者)/彦根市彦根中学校職員人権研修・講演「共に学んだ証彦根城東小「平和の誓」像から考える」講師(2006年1月16日)/マダンの風を淡海から―在日コリアンとの共生を考えるつどい・講演「消されたのは何か―「慰安婦」問題の真実を探る」講師(2月5日)/部落解放研究第13回滋賀県集会第2分科会(助言者、3月11日)/滋賀県教職員組合高校部セミナー・講師(3月19日〈予定〉)。また彦根市外国籍市民懇談会の委員にもなりました。
韓国留学時代に朝鮮の長鼓(チャンゴ)を習い、ずっと演奏仲間をさがしていたのですが、滋賀県で活動しているチングというグループに出会って仲間入りさせてもらいました。これ以外にも、地域でいろいろな出会いがあった一年だったので、今後もっと発展させたいと思います。
【教育活動】
二巡目となる朝鮮地域文化論B(隔年開講)は初年度とは趣向を変えてやってみようと講義案を一新しましたが、なかなかうまくいかず、悩みました。朝鮮文化論は毎年開講のためか、だいぶ落ち着いてきました。はりきって育休をとらずに「職場復帰」したわりには3回生のゼミ生の人数が一人と、こぢんまりとしたゼミになりました。夏のゼミ合宿では京都の丹波マンガン鉱山記念館を目指して行ったものの、原因不明の閉館で見学できず残念でした。もう一つの主な見学先、舞鶴の引揚記念館では、少ないながら朝鮮人に関する展示を発見したり、浮島丸遭難碑も何とか探し出して見学したりしました。卒論・修論は、今年は4回生二人だけだったので、じっくりつきあうことができて良かったですが、毎年「指導」の仕方について思案させられます。
【研究活動】
活字になったものとしては、「未公開資料朝鮮総督府関係者録音記録(5)朝鮮軍・解放前後の朝鮮」『東洋文化研究』6号(2004年3月)〈共著〉、「録音資料の「活用」作業に従事して--学習院大学東洋文化研究所所蔵「友邦文庫」録音記録を中心に」『史資料ハブ地域文化研究』(3)(2004年3月)で、前任校で始めた仕事がこれで一段落しました。あとは翻訳が二本です。梁鉉蛾「家族と社会
韓国的アイデンティティの暗い基盤--家父長制と植民地性」『
現代思想』 32(10)(2004年9月)、尹海東「植民地近代と大衆社会の登場」宮嶋博史他編『植民地近代の視座 朝鮮と日本』岩波書店(2004年)。学会のペーパーなどの翻訳は何度もしましたが、本格的な翻訳ははじめてで、苦労しました。
朴慶植文庫整理は、今年は予算が少なかったこともあり、コツコツと作業をすすめました。量的には今年度でかなり片づいたので、あとは、一般的な単行本・雑誌類以外の史料の整理を地道に続けていくことだと思っています。昨年度に朴慶植文庫を取材した内容を一部含むドキュメンタリー「HARUKO」が各地で上映され(その後DVD化)、遠方の知人から「見たよ」と連絡をもらったりしました。夏には、韓国のテレビ局がドキュメンタリー制作の一環で朴慶植文庫の取材のために本学を訪れることが数回あり、関心の高さを感じています。
◆
昨年、次男を自宅出産した関係で、地域の助産師さんとのご縁が深まり、滋賀県の出産環境を考える会主催のミニ・シンポジウム(2004年6月12日)や日本助産師会滋賀県支部教育委員会の研修会(2004年6月19日)などで話をする機会がありました。
産休後、「朴慶植文庫の整理事業を中断させられないし…」など、いろいろ考えた末、育休はとらず、育児時短を上限いっぱいの1日2時間申請して「職場復帰」をしました。研究者の勤務形態において育児時短がどう機能するのか、よくわからない面もありますが、担当コマ数や各種委員会等の校務は従前と同じようにやっているので、研究がなかなか進展しないことはカバー(?)してくれるだろうか、などと思い、今後も(上限いっぱいの)3歳まで育児時短を申請しようと考えています。
いきなり私事ですが、1月9日に、夫と長男、助産婦さんに見守られて、次男を自宅出産しました。陣痛開始からほぼ4時間の超安産で、産後も駆けつけてくれた実家の母の助けをかりて、慣れた自宅で穏やかに過ごすことができ、回復も早かったです。
自宅出産は、6年前に総合病院で長男を生んだ時から、病院での出産に疑問を抱き続けてきた帰結でしたが、いろいろな人に助けられ、縁にも恵まれて実際に無事何事もなく終えてみると、「何でこんなにいいことづくめのことを、ほとんどの人は選択しないのだろう?」と思います。今、日本では自宅分娩は1%以下で、残りは全部病院などの施設分娩です。本当に「目から鱗」の体験でした。
【教育活動】
産休に入る関係で、繰上げで土曜日に集中講義を行って、産休前に概ね終わらせましたが、やはりバタバタしてしまい、反省点が多いです。しかしはじめて実施してみた授業評価アンケートの結果は予想より良かったので、励みになりました。授業の最後に「元気な赤ちゃんを産んでください」とメッセージをくれた学生さんがいたことも嬉しかったです。私が3回生から直接受け持ったという意味では「1期生」となるゼミ生たちが、それぞれ頑張って卒論に取り組んでくれたことも嬉しかったです。
【研究活動】
妊婦生活と教員生活の両立で精一杯で、研究者としてはほとんど活動できなかった1年でした。「朝鮮金融組合婦人会について」『姜徳相教授退職記念 日韓・日朝関係史論文集』(明石書店、2003年)が出刊。4月に「批判と連帯のための東アジア歴史フォーラム」共同ワークショップに通訳を兼ねて参加。7月に東京外国語大学21世紀COEプログラム「史資料ハブ地域文化研究拠点」オーラル・アーカイヴ班定例研究会で「録音資料の「活用」作業に従事して-学習院大学東洋文化研究所所蔵「友邦文庫」録音記録を中心に」を発表。
朴慶植文庫整理は、量的には大分進めることができたと思いますが、より詳細な目録作成など、質的な面ではまだまだです。本年度は韓国国史編纂委員会が、昨年に本学との間に締結された学術交流協定に基づき、資料のマイクロフィルム化を申し出、膨大な量を撮影しました。来年度も継続の予定です。7月には、故朴慶植先生がつくられた学会である在日朝鮮人運動史研究会の大会が本学で開催され、遠方からも多くの方々に参加していただき、嬉しい限りでした。この大会にあわせて、これまで整理が完了した分について、地域文化学科として仮目録冊子を作成して関係者にお配りしたところ、大変喜んでいただけて良かったです。
本年度4月に着任し、ゼミを持つのも教壇に立つのも初めてで、ドタバタの一年でした。赴任前より「これだけはしっかりやろう」と思ってきた朴慶植文庫整理は、前任校で<研究所助手>として資料運用に携わった経験が役に立つだろうと思ったのですが、あまりの厖大さに、一年かけて何とか現状を把握し、重点研究の研究費でできる限り作業を進めた程度です。同文庫との関連では、5月に、韓国の国史編纂委員会と本学との間に学術交流協定が結ばれ、7月には国史編纂委員会の方が来訪、11月には同委員会からも講師をお迎えして記念シンポジウムを開きました(詳細は本号掲載の報告を参照して下さい)。また、国史編纂委員会から助成を得、朴慶植文庫の概略と、文庫中の録音資料についての報告書をまとめました。12月には滋賀大学経済経営研究所主催「旧植民地関係資料をめぐる戦前期文献保存のワークショップ~朝鮮・満洲・中国・台湾~」において本学の現状について報告を行いました。
【教育活動】
講義の準備や採点などは大変でしたが、良い勉強になりました。反省点を生かしてよりよい授業作りができるように頑張りたいと思います。初めての環琵琶湖文化論実習では、朝鮮通信使と近江商人について調べるグループを担当しました。近江商人については専門外で内心渋々でしたが、調べていくうちに明治に入って朝鮮半島に進出した近江商人がいたことがわかり、大きな収穫でした。今後調査を深められればと思っています。8月には学生と韓国旅行。実は6年ぶりの訪韓でしたが、私の唯一の特技「韓国語でしゃべっても日本人だとバレない」が通用したので大満足でした。県大客員研究員の蔡永國先生の紹介で韓国・國民大学校の教授・学生たちとの交流会も持て、学生たちにとっても有意義な旅行だったと思います。
【研究活動】
本年度4月に地域文化学科に着任し、ほぼ1年がたちましたが、まだまだ慣れないことが多く、ご迷惑をおかけしております。講義や卒論指導など全く初めてで、試行錯誤のくりかえしで反省点ばかりですが、何とか学期を終えることができ、ほっとしております。
私は朝鮮近代史、特に植民地期について研究しており、最近はジェンダーの視点からアプローチしようとしております。滋賀県立大学に赴任したので、今後は朝鮮に進出した近江商人のこと、県内の朝鮮人強制連行関連跡地、在日朝鮮人のことなど、「地域」と植民地という観点からも勉強し、講義や研究に反映させたいと考えています。
私は東京大学大学院総合文化研究科の地域文化研究専攻というところの出身です。在学中に専攻名について特に深く考えたわけではなく、自分自身としては主に歴史学の中に身を置いて研究してきたつもりですが、出身専攻と同じ学科名のところに運良く赴任できたので親しみを持っておりました。ところが、私が思っていた「地域文化研究」は英語ではArea Studiesで、様々なディシプリンを用いて一定の地域を総合的に研究するというイメージでしたが、本学科での「地域文化学」は、それとは異なる印象を持ちました。今度は学生時分のように深く考えずに放っておく訳にもいかないので、学科の会議などでの議論もうかがいながら、何かをつかみ取りたいと思っています。
これまでの、まだ短い研究者生活のなかで、自分なりに労力を注いできたのが資料の整理・公開の仕事です。前任校である学習院大学東洋文化研究所は朝鮮総督府関係者の収集したコレクション資料である友邦文庫を所蔵しており、主にその整理や活用を行いました。中でも、ほぼ半世紀前にオープンリールテープに録音された聞き取り資料の活字化は大変やりがいのある仕事でした。その意味で、本学でも「朴慶植文庫」整理に携わることができて光栄に思っています。資料は研究者の「研究成果」よりはるかに重要な意味を持って未来に残ります。特に植民地支配に関連する史料については、それを整理公開し、広く内外の ― 特に朝鮮半島の ― 研究者が利用できる環境を整えることは、日本の機関の義務であるとも考えています。特に近年、韓国では国家的プロジェクトとして資料の整理や電子化などが急ピッチで進んでおり、その恩恵に十二分にあずかりながら研究するにつれ、日本の立ち後れた状況はあんまりだという思いが強くなります。
前任校では任期付きの助手だったこともありますが、大学改革の荒波に直接的に巻き込まれることはありませんでした。そろそろそういうわけにはいかなさそうです。何事も学びつつ自覚を持って取り組んでいきたいです。何卒よろしくお願い申し上げます。
最終更新日 2011/09/28
|
最終更新日 2012/01/26 |