カリキュラム

「人間関係学科」は、人間生活を営んでいくうえで、一番身近な衣・食・住や人間関係を通して、現在の人間生活を研究・分析します。変化していく“生活”のあり方を追求することによって、豊かで文化的な生活を創造していくことをめざします。
専門科目の例
心理学基礎
後藤崇志
心理学を行動と精神過程を研究する科学と考え、行動と精神にかかわるいくつかの領域を概説します。人間行動の差異と共通性が分かるようにすすめます。 |
コミュニケーション論
細馬宏通
日常会話におけることばと動作の問題を、会話分析、ジェスチャー研究から考察します。発語と身体動作とはどのようなタイミングで産み出されるか、目の前にない空間を身体動作によってどう共有するかなどについて学びます。 |
臨床心理学
松嶋秀明
人の心を理解することは、他人を理解するだけでなく、自分自身への理解を深めることでもあります。この講義では臨床心理の基本(心の病、心理アセスメント、心理療法)を講義・実習・ビデオ教材を通して学びます。 |
発達心理学
上野有理
胎児期から乳幼児期、少年期を通じて、こころがどのように発達していくのか、他者理解やコミュニケーション能力、さらに、物理的環境とのかかわりにおいて発揮される知性の発達を概観し「自己」が育つ過程とメカニズムを考えます。 |
比較認知発達論
上野有理
ヒトに特有な言語や複雑な社会的知性はどのような進化的基盤を有するのか、現生の霊長類の認知や行動の発達を比較することで、ヒトの心の霊長類的起源と種独自性が明らかになります。本講では、最近のこの領域の研究成果を学びます。 |
人間行動論
細馬宏通
19世紀末以降の映像作品について、視聴覚がどう組織化されてきたかという知覚の問題、人の身体はどのように表されてきたかという表象の問題、その時代にどのようなモードが流通していたかという歴史の問題を扱います。 |
人間形成論
木村 裕
貧困や格差、環境破壊など、現代社会には世界中の人々の協力なしには解決できない問題がたくさんあります。では、こうした問題を解決し、住みやすい社会づくりに参加できる人を育てるためには、どのような場で、どのような教育活動を行うことが必要なのでしょうか? この講義では、こうした視点から「教育」という人間形成の営みを見つめ直します。 |
教育学概論杉浦由香里
なぜ、どうして、いつから人々は学校に通うようになったのでしょうか。教育の営みや思想を人類史的視点から捉えるとともに、近代教育制度が成立する過程を学ぶことを通じて、現代の教育や学校のあり方を問い直します。
|
社会問題の社会学
中村好孝
ひきこもり、いじめ、貧困、犯罪…様々な社会問題があります。本講義では、それらの概要とともに、しかしそもそもある現象は、何によって、どのようにして、社会問題だとされるのか?と考える社会学的な観点を学びます。 |
生涯学習論
原 未来
「学習」は、学校だけでなく、様々な場で、多様な発達側面を含みながら展開されます。
この講義では、学校教育内外の教育や学習の実態を取り上げながら、学ぶこととは人々にとってどのような営みなのかを考えていきます。
|
社会調査方法論
大野光明
社会調査の企画・設計から資料・データの収集と整理までの具体的な過程と方法を学びます。講義の中では、質問紙の作成等においてグループ学習をとり入れます。 |
社会変動論
丸山真央
現代社会は変動のただ中にあります。ヒト、モノ、カネ、情報は国境を越えて飛び交い、国家やコミュニティや家族といった従来自明だった社会制度はどれも変化を余儀なくされています。そうした変化のからくりを読み解く社会学の視点と方法を学びます。 |
|

△ニホンザルの観察実習 |

△カウンセリング論演習 |
|
![]()
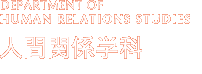


 大学ニュース一覧
大学ニュース一覧 人間関係学科オリジナルサイト
人間関係学科オリジナルサイト
