終戦から五十年余りが過ぎ、私たちのように戦争を知らない世代が増え、どんどん戦争を語る人が減っている。そのような時代の移り変わりの中で、歴史の生き証人である祖父の体験を、またその当時の生活の様子を家族への手紙や日記を通して伝えることができればと思い、この展示を企画した。 祖父は農村の長男に生まれたが、太平洋戦争中は衛生兵として二度出征した。祖父の父が早くに亡くなっていたので、農繁期には老人や女・子どもばかりで苦労をしたという。しかしそのような状況の中でも、お国の為、出征している兵士の為と誰も弱音を吐かずに必死で働いた。祖父と祖母の手紙のやり取りからはその当時の情景がありありと目に浮かぶ。 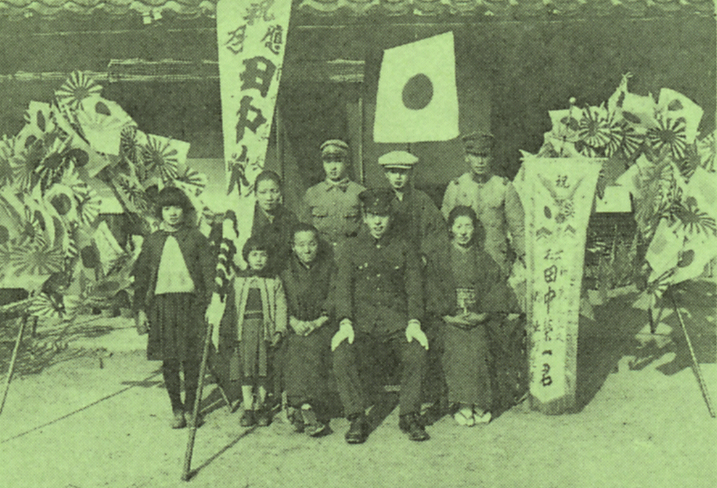 わたしたちのように戦争を知らない世代は、戦中・戦後のように物のない貧しい暮らしをした経験がない。また家族が一つ屋根の下で生活できることを当たりまえと思い、家族の絆やありがたみというものを実感する機会が少ないと思う。戦争で家族や親しい人たちと離れ離れにならなければならなかった一兵士の手紙から、家族の大切さをも訴えることができたならばうれしいと思う。 残念ながら、今回展示に使った手紙には外地(海外)から出されたものはあまり含まれていない。それらのほとんどは祖父の意志により、栗東町に寄付されたからである。とはいえ、手元に残るものは出征前の心情を吐露したものなど私的な内容のものであり、ありのままの心情が良く表れている点で貴重な資料といえる。 また今回、従軍日記や衛生兵ノート、戦地や陸軍病院で写した写真なども併せて出展した。これらによって観覧者に、戦争の非情さを肌で感じとってもらえるようにと考えた。 「赤紙が来たら、親が死んでも出征しなければならない」と言われたほど、召集令状は絶対背くことの出来ないものだった。家族や近所の人達に盛大に見送られ、兵士たちは出征する。しかし彼らは直接戦地に送り込まれるわけではない。一旦召集された後、それぞれの兵種ごとに分けられ、実戦のための訓練を受ける。 衛生兵の場合は他の兵士とは異なり、国内に設けられた軍隊の病院で勤務をしながら、看護の勉強をしていた。治療のみならず、戦地で衛生兵がとるべき行動や心得などについても、徹底して教え込まれた。 そうした厳しい訓練の後、外地の前線に送り込まれていったのである。  郵便はこの時代、最もポピュラーな通信手段であったが、不確かなものでもあった。特に戦地と国内をまたぐ郵便は、相手に届けられる保証はまったくなかった。戦争末期には届くほうが珍しい程低い確率だった。 戦地にいる兵士たちが家族や友人に手紙を送る場合、2つの郵送手段があった。 1つは、軍需物資などを輸送する貨物船に載せて日本まで届けてもらう方法。これは相手の手元に届くまでにずいぶん時間がかかる上に、もしその船が敵軍に撃沈された場合はあきらめなければしかたない。しかも相手方に無事届けられたかどうかは、相手からの返信以外確かめる術もないのだ。 もう一つは航空便で届ける方法。こちらの方が、船便よりもはるかに速くて確実である。しかし飛行機といっても今のように大きなジェット機などない時代である。一度に運ぶ重量には制限があり、その利用は月に何回と決められていた。 そのため兵士たちは、大事な、あるいは急を要する郵便は航空便で、日常的なものは船便で、というように使い分けていた。 とは言え、どちらにしても検閲の眼が光っているので、伝えたいことをそのまま書くわけにもいかなかったのだが。 召集された兵士には身内や隣組・学校から千人針や絵など、様々な慰問の品が贈られた。その中でも兵士にとって一番の楽しみは家族の面会や手紙だった。 軍隊が戦場に移動すると、手紙が唯一の家族との連絡手段になる。故郷への思いはますます募り、兵士は行軍のわずかな合間を縫ってせっせと手紙を送る。家族も戦場の兵士の慰めになるようにと、銃後を守る人々の暮らしぶりを伝えた。 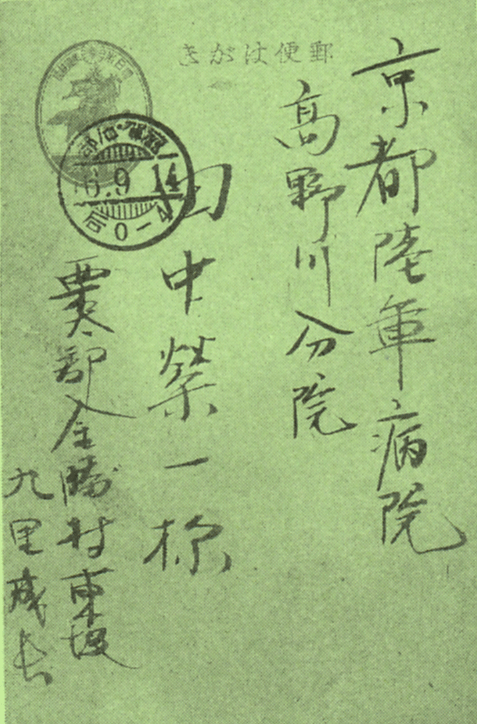 軍隊では敵に作戦を知られないよう、郵便には所在地や詳しい戦況などを書かないことが義務づけられていた。 また思想統制のために、戦争に反対するような言葉や死を恐れる気持ちなどを表すことも許されなかった。そして兵士もお国の為に潔く戦って死ぬことを名誉とする教育の下に、“恐怖”という人間ならばあって当然の感情をも自ら否定せざるを得なかったのである。 兵士が出すものも受け取るのも、はがきや手紙は文面まで検閲され、不適切な文章は墨で黒塗りされるなどの処分がなされた。検閲された郵便には検閲済のハンコと検閲者の印が押された。非常の時には検閲印の代わりに、はがきの端をはさみで切ってしまう場合もあった。たとえその部分に精いっぱい気持ちを込めた文章が書かれていても、である。 兵士らは検閲の眼をごまかす為に、時には「〇〇〇な気持ちです」などと暗に言いたいことをほのめかす手段を使うこともあった。 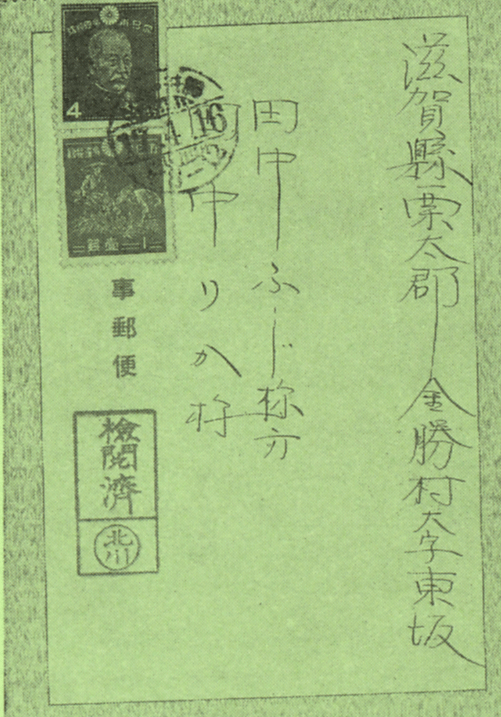 祖父は衛生兵として従軍したが、その頃のことを思い出すと今でも涙が出るという。 野戦病院や衛生隊には一通りの手術道具と薬などが揃っていたが、軍医は 150人の兵隊に2人の割合でしかいなかったため、結局はたいした治療もしてあげられなかった。軍隊についていけない重体の患者には手榴弾を渡して、置き去りにする場合も少なからずあったという。 唯一の慰めは家族からの手紙だったが、それも検閲にひっかかったり郵便船が沈没したりで、必ずしも届くとは限らなかった。運よく手元に届いても、恋文など送られてこようものなら、みんなの前で読まされ、仲間の兵士たちにからかわれた。そのような状況では、妻や恋人に手紙を書くにしても、感情を素直に書くことすら出来なかったのである。 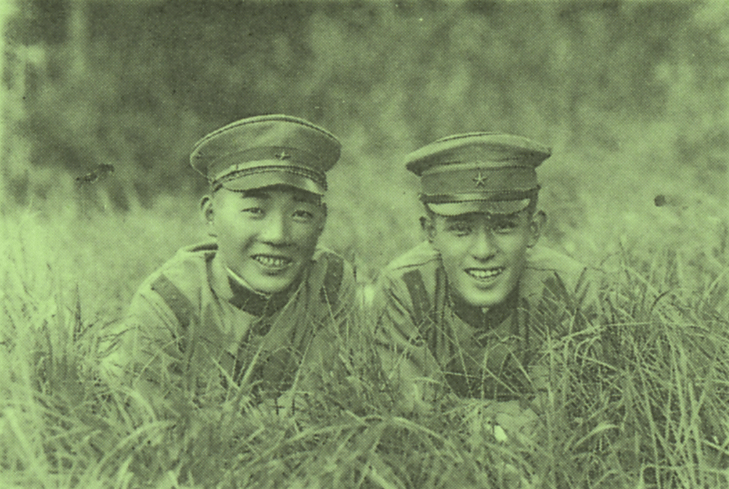 当時は、一旦軍隊に入営した以上は軍務優先にて、自分の青春・家族・故郷を忘れ、皇軍の戦勝を祈りつつただ軍務に努めたが、時折、戦閑の夜等には故郷の安泰と家族の健康を願い、望郷の想いに南十字星の下から故郷を偲んで涙ぐむ事もあった。 おばあちゃんは、おじいちゃんが戦争に駆り出されることになったから、この家に嫁いできたんや。 おばあちゃんのお父さんは、おじいちゃんに嫁がせるのはあまり乗り気ではなかったけど、この家にはお父さんがいなくて働き手がなかったから、かわいそうに思ったんや。家が近所やったし、親戚でもあったから、放っておけへんかったやな。おばあちゃんは別におじいちゃんと愛し合って結婚したわけじゃなくて、家の手伝いをするためにもらわれたんや。昔は親が「この家に嫁ぎなさい」と言ったら、その通りにするしかなかったからな。 おじいちゃんは出征するし、次男はそれより前に戦争に行ってたし、学校を出て働き盛りの妹も勤労奉仕として軍需工場で働いていて、それより下の弟妹は学校行きの子供やった。 お姑さん、おばあさん、子供2人におばあちゃんと男手がない時でも、大きな牛をひっぱって田んぼを耕したもんやった。それでも私らを守るために戦場で戦ってくれてるおじいちゃんらのことを思うと、文句なんか言えへんかった。 あの頃頑張りすぎたから、そのせいで今でも神経痛に悩まされてるんや。  |