| 尼崎を訪れて |
尼崎は平安時代頃から港町として発展してきた、中世有数の自治都市である。事前に尼崎について調べていく中で私が最も面白く感じたのはこのことについてである。自治都市として私が思いつくのは堺などの都市で、あまり尼崎にはそういうイメージがなかった。尼崎について調べていくうちに尼崎には有力な問丸ら商人がいたこと、住民の力が強く一度は織田信長の軍勢を退けたことがあることなどを知り、活気のあふれる都市だったのだろうなと自治都市尼崎を想像していた。
私は尼崎を訪れたことは初めてだった。尼崎をバスの中から眺めながらいろんなことを考えた。マンションや住宅が立ち並ぶ地域、高い建物が立ち並ぶ地域などを通り過ぎながら「ここは昔々は海の底だったんだ」などと少し考えていた。事前調べで縄文時代は海の底だったと知ったためだ。また先ほども書いたように、有数の自治都市であった尼崎の様子はどんなだろうと思いながら眺めていた。
尼崎に着いて、富松城を訪れた。まず、富松城についての説明や富松城に関する活動の内容、まちづくりなどについての説明をしてもらった。これまでの活動やその成果を聞いていて、私は「尼崎は、今も昔も活気に満ちた町なのだ」と感じた。そう感じた理由には他に、お話を聞いている中で聞いた女子高生の活動がある。富松城跡についての研究活動を行い、城跡の保存活動を展開する地元グループとの交流を深めている2人の女子高生。とても意欲的で努力家でだ。自治都市であった時代の活気は現在の尼崎にも健在で、また女子高生の興味を惹きつける魅力が富松城にあるのだと思った。
その後、富松城のお堀の跡に案内してもらい、そこでも説明してもらった。「城」と聞くと想像するのはやはり石垣のある城郭で、この富松城は街の真ん中にポンとあって城跡という感じもあまりしなかった。ただ堀の跡はしっかりうかがえ、とても貴重な城跡なんだと思った。
旅行後、もらった資料をもう一度見た。旅行中には気づかなかった面白い取り組みをいくつも見つけた。富松城一夜城体験学習で富松城土塁復元に挑戦したり、手作り大絵馬に富松城を守る願いを託し奉納したりといったものだ。尼崎の地域誌にも何度か掲載されているし、研修・講座・シンポジウムが行われている。まちづくりには、新しい名所を作るより、自分の地域の知識を増やし、それを広める活動を行い、周囲からの認知を高めることが必要であると思う。そのどれもが進められている。写真を見せてもらったが、鎧を着て行われたパレードなどは直接自分で感じることができるので、見る人も興味がわきやすいだろうと思う。富松城は大切な城跡で、尼崎の自治都市民を思わせる活発な地元の人たちによって守られている、それを強く感じた旅行だった。 |
| (澤田 久美子) |
|
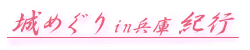
 もどる
もどる もどる
もどる もどる
もどる もどる
もどる もどる
もどる もどる
もどる もどる
もどる もどる
もどる もどる
もどる もどる
もどる